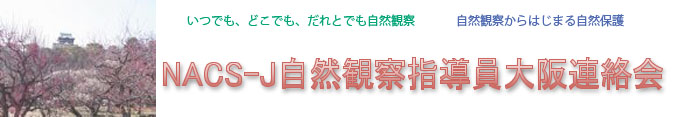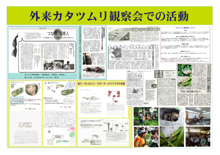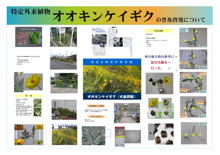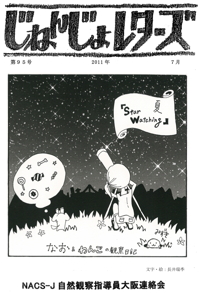活動について
ネットワーク

大阪連絡会の会員の方々には、自分の住んでいる団地の構内で観察会を開いている方、障害をお持ちの方でも参加しやすい観察会を開いている方、都市公園を中心に観察会を開いている方など、自然観察会をやっておられる自然観察指導員の方がいます。
もちろん、観察会を開いていない自然観察指導員の方でも、通勤の行き帰りに目にとまる川の変化について記録されている方がいて、それを市に提言されたり、母と子だけの親子観察会をのんびりとやり続けられている方もいます。その他にもNACS−Jだけでなく他の団体(保全協会、日本野鳥の会、ネイチャーゲームの会、WWFJなど)にも入っておられたり、自然に対する関心の高い方々の集まりであり、そう言った方々の情報交換を行っているネットワークです。
こんな活動しています
生物多様性の重要度を認識するために、CEPA(Communcation, Education and Public Awareness)、広報、教育、普及啓発活動に、会として、大きく関わっています。
特に、具体的な活動としては、(特定)外来生物問題(オオキンケイギクなど)の普及啓発があります。
大阪という都市部では、外来生物を多く見ますが、外来生物を悪者にしようというのではなく、特定外来生物の挙動、広がり方が分からない現状、注目をしています。 具体的な提言に活かせる方向の取り組みに繋がればと思っています。 <特定外来生物ではありませんが、外来カタツムリのヒメリンゴマイマイについて、勉強会を開催したり、各所に情報提供し、普及に努めました>
会員の意識を高めるような取り組みをすることで、一般の人と一緒に、自然環境に対し、関心が上がればと考えています。
他団体との協働や関わりなど
(いろいろと関わっていて、できれば、下記に参加してくれる人を求めています)
- 生物多様性かんさい(メンバーとして参加)
- モニタリング1000里地調査(コアサイト:枚方・穂谷。調査員として参加)
- タンポポ調査西日本2010(実行委員としての参加)
- きんき環境館(パートナーシップ団体として登録。生物多様性意見交換会参加)
- セミの抜け殻しらべ市民ネット
- 自然観察指導員・近畿圏交流会(滋賀、京都、奈良、愛知、兵庫、鳥取、和歌山など各連絡会ネットワークとML通して情報交換)
他にもいろいろ関わっています(登録だけになっていますが、「かけはし(大阪環境パートナーシップネットワーク)」 など)。
ポスター形式での活動紹介
様々な場で活動紹介した際に、ポスターを作成したものです。
詳細PDFからダウンロードしてご覧下さい(容量が大きいです)
広報・教育・普及啓発活動(CEPA)
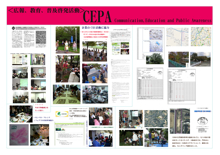
外来生物の勉強会、企業から依頼されたCSR活動に協力(セミの抜け殻調べ観察会、水辺の外来種しらべ)、子供達とのセミの抜け殻しらべ、フェアなどの出展協力など